Message
医局長挨拶
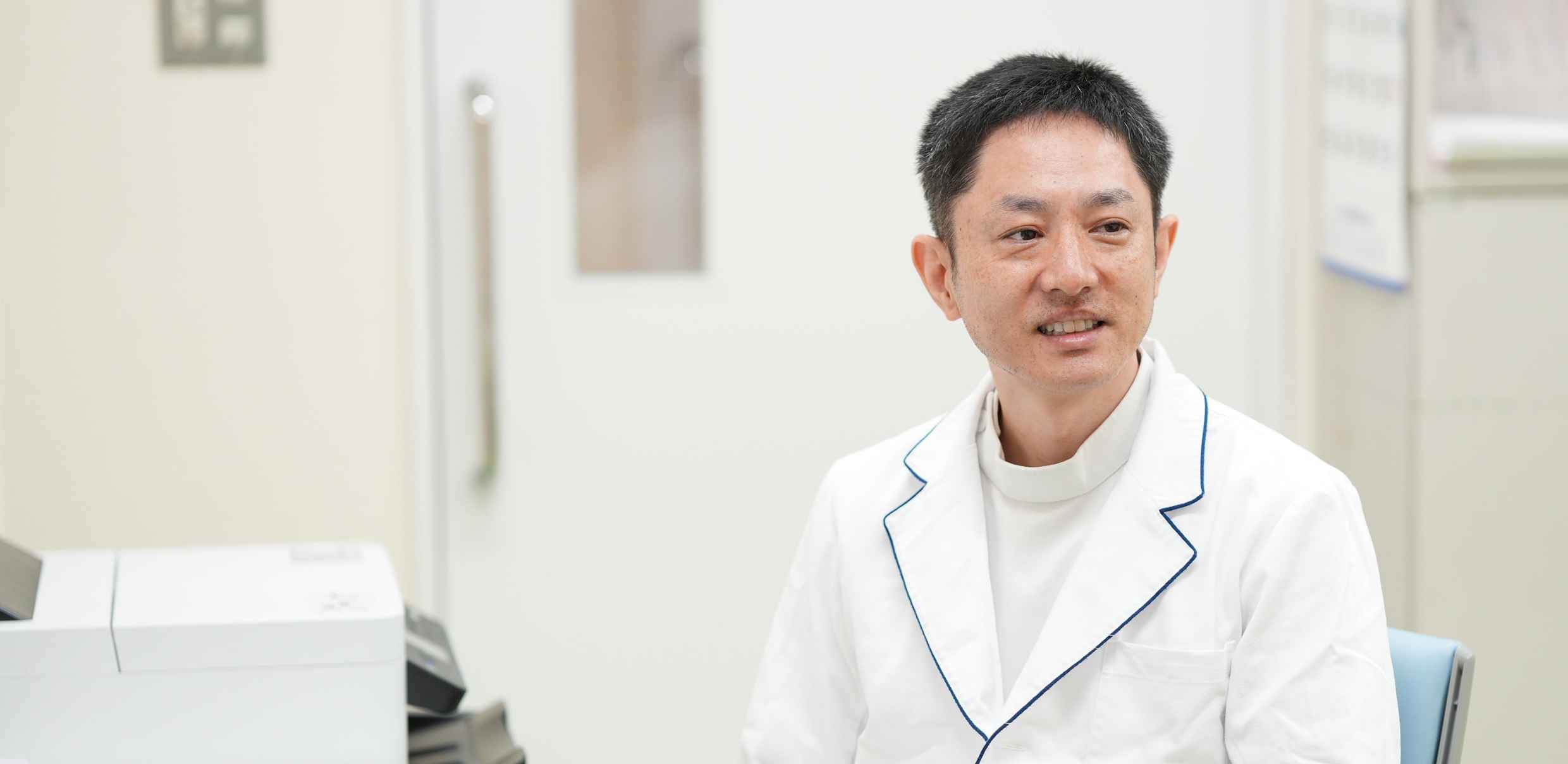
大分の医療の現状
これからの総合診療医について

最も新しい19番目の専門医
総合診療医
総合診療医は、一通りの病気を診ることができる点が武器になります。
総合診療医が3人程度いれば、その地域の医療は成立すると言われているため、総合診療医が重宝される存在となることは間違いありません。
最も新しい19番目の専門医である総合診療医に、漠然とした不安を感じている人もいるかもしれません。
しかし、当科も創設から歴史を重ねる中で、さまざまな将来の道筋を示せるようになってきました。モデルケースが少ないことに関しては、実際に総合診療の病院で実習し、ジェネラリストとして働くことはどういうことかを体感する機会を設けています。
その働いている姿を見れば、総合診療医として働き続けることへの不安はなくなることを確信しています。
総合診療医の仕事は、いい意味での「隙間産業」です。どこの科に属するかわからない患者さんを救うため、専門性に特化した臓器専門医を助けるために存在します。
医療界の「何でも屋」として医療の土台を支えること、そして、他科専門医が活躍する環境を整えるという、マネジメント機能を担っていることにも誇りを持っています。

悩んでいる方にこそ勧めたい、総合診療医への道
進路に悩んだ時は、「最終的にどういう医師になりたいか」、「どういう働き方をしたいか」を考えてみましょう。
目標とする医師像につながる道を選べばいいと思います。
進路に悩んでいる学生の皆さんに、私からお伝えしたいのは、「道は変えられる」ということ。
後戻りできないと思うと悩んでしまいますが、人生はいつでもやり直しができるものです。
そのときの気持ちに素直に、やりたいことをやってみてはどうでしょうか。
私は2002年に大分大学医学部を卒業し、総合診療部(現在の総合診療・総合内科学講座)に第1期生として入局しました。
私の場合は、専門科を決めきれなかったということが、当科を選んだ大きな理由です。
「町医者になりたい」という大まかな希望しかなかったので、できたばかりの科に所属して、幅広く知識・技術を身に付け、最終的に専門分野を選択すればいいのではと考えました。
結局、「人」を診る、この仕事にやりがいを感じ、ずっと当科に在籍しています。

1人の患者さんを
多角的に診れる喜び
臓器専門医は臓器→ミクロ→遺伝子というように、対象がどんどん狭く詳しくなっていきますが、総合診療医は患者さん→家族→地域と対象を広げていくのが大きな特徴です。
総合診療医には、医師としての技能のほかに、コミュニケーション能力、ネットワーク力などが必要となります。
患者さんや家族と信頼関係を構築し、さまざまな情報を引き出さなければなりませんし、看護師やケアマネジャーとの連携も不可欠です。また、臓器専門医を紹介する場合は、同職種間のネットワークが必要になります。
総合診療医は、臓器専門医と比べて、より「人間力」を必要とするオールラウンダーです。
1人の患者さんに寄り添い、さまざまな視点からアプローチできる点が、総合診療医の魅力です。患者さんの言葉にヒントを見出したり、心理的・社会的背景から病気の原因を探ったりするのは時間がかかります。しかし、複数の科を受診しても痛みや熱が取れなかった患者さんに診断がついたり、痛みが和らいだりしたときは非常に感謝され、やりがいが感じられます。
当科では幅広く学びながら、その後の進路を決めることができる点がメリットのひとつです。
臓器専門医のほか、感染症・救急・研究・在宅医療などの得意分野を伸ばす選択肢もあります。
当科はみんな仲が良く、楽しんで仕事をしています。ライフワークバランスも含めて、自分が楽しく充実していないと、いい仕事はできないと考えているからです。
皆さんの入局を心待ちにしています。








